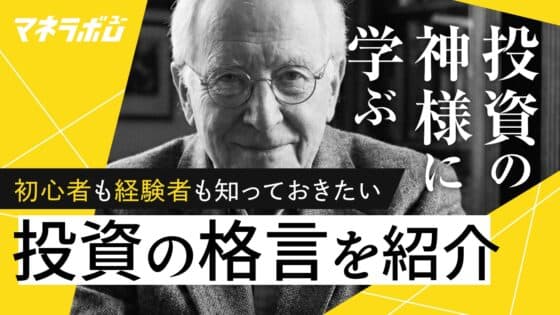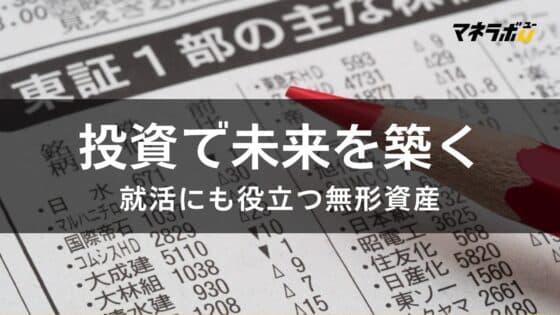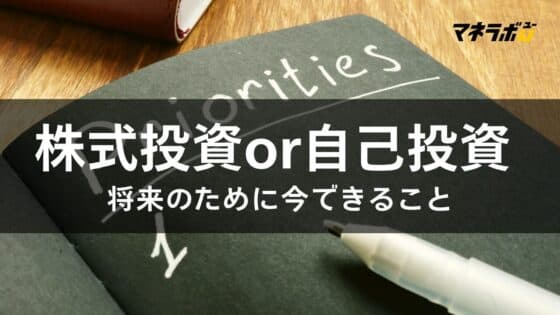~お金が“増え続ける”仕組みを知ろう~
こんにちは。
これまでの連載を通じて、資産運用の基本やインフレ対策、積立投資の効果について学んできました。
そこで今回のテーマは、資産運用において“最も重要な原理”とも言える「複利」です。
「単利」「複利」という言葉は聞いたことがあっても、その違いを正確に説明できる人は意外と少ないかもしれません。
しかしこの2つの違いを知っているかどうかは、長期的な資産形成において大きな差を生みます。 この記事では、単利と複利の基本的な仕組みから、数字での比較、そしてどんな場面で複利が最大の効果を発揮するかまでを、わかりやすく解説していきます。
単利とは?〜「元本にだけ」利息がつく仕組み〜
単利とは、「最初に預けた元本」にのみ利息がつく計算方法です。
たとえば、100万円を年利5%で単利運用した場合、1年後の利息は5万円。2年目もまた5万円、3年目も5万円…と、毎年同じ金額の利息がつきます。 つまり、単利では「増えた分」には利息がつかないため、増加スピードは一定で、直線的です。
単利のイメージ(元本100万円、年利5%)
| 年数 | 資産額 |
| 1年目 | 105万円 |
| 2年目 | 110万円 |
| 3年目 | 115万円 |
| 10年後 | 150万円 |
10年で50万円の利息がつき、合計で150万円になります。堅実ではありますが、劇的には増えません。
複利とは?〜「増えた分にも」利息がつく仕組み〜
一方、複利とは、利息が元本に加算され、その合計にまた利息がつくという計算方法です。
つまり、「増えた分にも、また利息がつく」という仕組み。
これが時間とともに大きな差を生み出します。 先ほどと同じく、100万円を年利5%で運用する場合、1年目の資産は105万円。
2年目はこの105万円に5%の利息がついて110.25万円、3年目はそれにまた5%がついて…というように、年々増えるペースが上がっていくのが特徴です。
複利のイメージ(元本100万円、年利5%)
| 年数 | 資産額(約) |
| 1年目 | 105万円 |
| 2年目 | 110.25万円 |
| 3年目 | 115.76万円 |
| 10年後 | 162.89万円 |
同じ100万円でも、単利より約13万円多く資産が増えていることがわかります。
そして、この差は時間が長くなればなるほど、投資する金額を増やすほど大きくなっていきます。
単利と複利の違いをわかりやすく比較
| 項目 | 単利 | 複利 |
| 利息の対象 | 元本のみ | 元本+過去の利息 |
| 増え方 | 一定(直線的) | 加速度的(指数的) |
| 長期運用効果 | あまり変わらない | 時間が経つほど差が広がる |
どちらを選ぶべき?資産形成では「複利」が基本
では、私たちがこれから資産を作っていくとき、どちらの方法を選ぶべきなのでしょうか?
資産形成を長期的に考える場合には、複利を活かした運用が有効な選択肢の一つとされています。
特にNISAのつみたて投資枠やiDeCoなどの非課税の優遇を活用した長期積立投資では、複利の力が最大限に活かされます。得られた利益を使うのではなく、再投資することで運用効率を高められるのです。
投資信託を通じて、毎月積み立てながら複利で資産を増やしていくことで、時間をかけて資産が成長していく可能性があります。
「複利を効かせる」ために必要な2つの条件
複利は自動的に働くものではありません。最大限に活用するためには、次の2つの条件を満たすことが大切です。
1. 時間(長く続けること)
複利は「時間の経過によって効力を発揮する仕組み」です。短期ではほとんど効果を感じられませんが、10年、20年と続けることで雪だるまのように資産が膨らみます。
2. 利益の再投資
得られた利益をそのまま引き出して使ってしまうと、複利の効果は止まってしまいます。
利益を再投資に回すことが、複利を活かす運用のポイントです。
たとえば、投資信託を選ぶ際に「分配金再投資型」を選択すれば、利益が自動的に再投資されます。これにより、自動で複利効果の恩恵を受けられます。 なお、「複利=必ず資産が増え続ける」というわけではなく、市場環境や運用成績によって結果は変動します。長期的な視点と適切なリスク管理が大切です。
まとめ:複利という「時間を味方にする力」を理解しよう
- 単利は「元本にだけ利息がつく」、複利は「増えた分にも利息がつく」
- 長期になればなるほど、複利の方が大きな差を生む
- 複利の力を最大化するには、「時間」と「再投資」がカギ
- 投資信託やつみたてNISAは、複利を活かすための有効な手段
お金を増やすために、何か特別な能力や一発逆転の勝負は必要ありません。
むしろ、「複利の仕組み」を早く理解して、少額でも長く続けていくことが、着実に資産を築くための一番の近道です。
実際に、長期投資はリスクを分散しやすく、複利の効果も期待できるため、堅実に資産形成を進めたい人にとって有力な選択肢とされています。
一方で、短期間で大きな利益を狙うのはプロでも難しいと言われており、安定的な成長を目指すのであれば、長期的な視点で少しずつ取り組む方法が現実的かもしれません。
次回予告
次回は、第16回「金融商品って何がある?初心者が知っておくべき種類と特徴」をテーマに、投資信託、株式、債券、保険など、身近な金融商品の基礎を一つひとつ解説していきます。