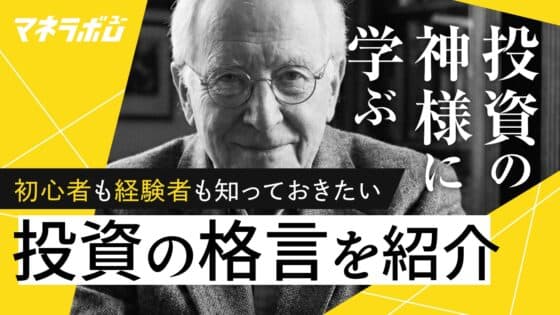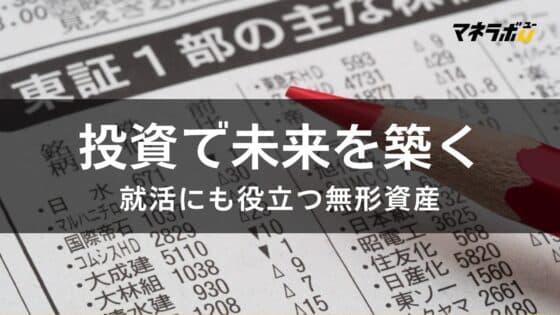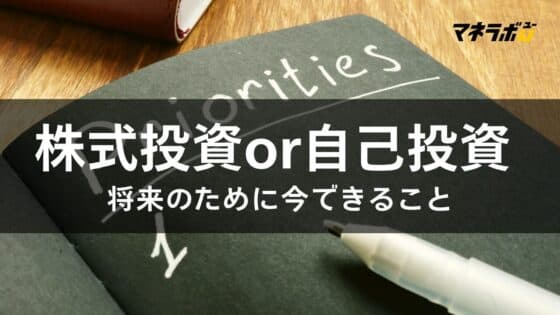~「物の価値が上がる時代」に、損しないための知識と選択~
こんにちは。
最近、「なんとなく物の値段が上がっている気がする」と感じたことはありませんか?実際に、ここ数年はさまざまな商品やサービスの価格が上昇しています。
これは、「インフレーション(インフレ)」と呼ばれる経済現象の影響です。
インフレは、私たちの生活の中でじわじわと進行し、お金の「価値」を下げるという、見えにくい形で私たちに影響を及ぼします。
今回は、「インフレとは何か?」「なぜ起こるのか?」「その影響を受けないお金の使い方は何か?」を、大学生にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
インフレとは?日常に潜む“静かな値上げ”
インフレとは、モノやサービスの価格が全体的に上昇する現象のことを指します。
言いかえると、同じ金額で買えるモノの量が減っていく状態です。 たとえば、去年までは500円で買えていたランチが、今年は550円に値上がりしているとしたら、それはインフレの影響が現れている例です。
表面的には「ちょっと高くなった」だけに見えるかもしれませんが、裏側ではお金の「価値」自体が目に見えない形で減っているということになります。インフレが起きても通帳の残高が減るわけではないため、「見えない泥棒」と呼ばれることもあります。
インフレが起こる理由とは?
インフレが起こる背景には、経済全体の構造や政策による明確な原因があります。代表的な3つの要因を見てみましょう。
1. 需要と供給のバランスの変化
多くの人が商品やサービスを「買いたい」と思う一方で、それを提供できる量が足りていない状況を考えてみましょう。この場合、企業は価格を引き上げても売れるため、価格全体が上昇していきます。
これを「需要が供給を上回るインフレ(ディマンドプル・インフレ)」と言い、景気が良い時や消費が活発な時に起こりやすいパターンです。
2. 原材料やエネルギー価格の上昇
原油や小麦などの資源価格が上がると、それをもとに作られる商品やサービスのコストも上がります。
そのコスト増加が価格に転嫁されることで、物価全体が上がる「コストプッシュ・インフレ」が発生します。
3. 金融政策による貨幣量の増加
中央銀行が低金利政策を取ったり、大量にお金を市場に供給すると、世の中に出回るお金の量が増えすぎて、その結果としてお金の価値が下がり、物価が上昇することがあります。
これを「貨幣量の増加によるインフレ」と呼びます。 これらは単独で起こる場合もありますが、実際には複数の要因が重なってインフレが加速するケースも多く見られます。
つまり、インフレは「なんとなく起きるもの」ではなく、経済全体の動きによって引き起こされる現象なのです。
インフレがもたらす“見えない損失”
一見、物の値段が上がるだけに見えるインフレですが、実際にはお金を持っているだけで損をするという側面があります。
たとえば、タンスに10万円を入れて5年間そのままにしておいたとします。
その間に年2%ずつ物価が上昇していれば、5年後にその10万円で買えるものの量は、実質的に9万円分程度に目減りしてしまいます。
つまり、「お金を使っていないのに、価値は勝手に減っている」状態になるのです。 この“見えない損失”こそが、インフレの怖さです。
つまり、ただ貯金をしているだけでは、インフレ時にお金の価値を十分に保てない可能性があります。インフレ率以上の利回りでお金を運用しないと、持っている資産の価値は減ってしまうのです。
インフレの影響を受けやすいお金の置き方
インフレの影響を受けやすいお金の置き方の例としては、次のようなものがあります。
まず最も典型的なのが、現金での長期保有です。
タンス預金や、利息がほとんどつかない普通預金に何年も預けたままにしていると、インフレによってお金の価値が徐々に減ってしまいます。 また、利回りが非常に低い資産(超低金利の定期預金や、予定利率の低い保険商品など)も、インフレの進行スピードに追いつけないことがあります。
結果的に、「増えているように見えて、実質的には減っている」状態になりかねません。
インフレに強いお金の使い方とは?
インフレに対応する方法としては、節約に加えて、お金の置き方や使い方を見直すという選択肢もあります。
以下は、大学生でも検討できる“インフレに強い”選択肢です。
株式や株式型の投資信託
企業は原材料費や人件費が上がれば、それに応じて販売価格を上げることで利益を確保しようとします。
そのため、企業の価値に投資する株式や株式型の投資信託は、インフレに強いとされる資産の一つとされており、長期的な視点での資産形成を検討する際の候補になります。
特に、S&P500や全世界株式に連動するインデックスファンドは、物価上昇とともに長期的に成長してきました。実績があるだけでなく、低コストで長期投資にも向いているため、初心者にもおすすめです。
実物資産(不動産・金など)
土地や建物、金などの「実物に裏付けられた資産」は、物価と連動して価値が上がる傾向にあります。
大学生のうちは直接的に不動産を購入することは難しいかもしれませんが、REIT(不動産投資信託)や金ETFなどを通じて、少額から投資することも可能です。
自己投資(スキル・経験・資格)
インフレの影響を受けない、むしろ価値を上げていける投資の一つが「自分自身への投資」です。つまり、「自分自身の能力を高めて、より多くの報酬を受け取る」という考え方です。
語学力、専門知識、プログラミングなどのスキルは、社会の変化に強く、将来の収入や選択肢を広げる「人的資本」になります。
自己投資は、インフレに左右されないどころか、むしろ社会的な価値を高めていくための強力な武器です。就職したあとも、継続的に「社会で求められている知識やスキルがないか」「人脈を広げるための投資方法はないか」を考え、自己投資を意識してみてください。
お金を“守る”ことは、増やすことと同じくらい重要
投資というと、「いかにお金を増やすか」に意識が向きがちです。
しかし、物価上昇が続くこれからの時代においては、お金の「価値を守る」視点が欠かせません。 たとえ大きな利益が出なくても、インフレによる価値の目減りを抑えることができれば、それは立派な「防衛的成功」です。インフレが生活や資産に与える影響を知り、適切な対応をすることで、大切な資産を守ることにつながります。
このように、資産運用は、攻めだけでなく守りも大切なのです。
まとめ:未来のお金の価値を守る「意識」と「行動」を
最後に、今回のポイントを振り返ってみましょう。
- インフレとは、モノの値段が上がり、相対的にお金の価値が下がる現象
- インフレが起こる背景には、需要と供給のズレ・資源価格の高騰・金融政策の影響がある
- 現金や超低金利商品にお金を置いておくと、知らぬ間に損をする可能性がある
- 株式、実物資産、そして自己投資はインフレに強い「お金の置き方」である
- 資産を増やすだけでなく、価値を守ることも大切な資産運用の目的
これからの時代は、「お金を持っているだけで安心」ではいられません。
お金の“価値”を守るための選択と行動を、今日から少しずつ始めてみましょう。
次回予告
次回は、第15回「単利と複利ってなにが違うの?」をテーマに、資産を着実に育てる鍵となる「複利」の本質と、単利との違いを具体例で解説していきます。