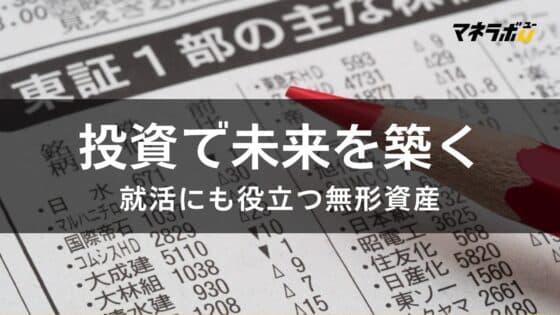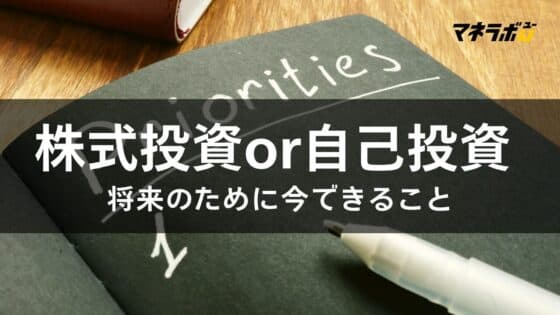~仕組みと選び方をわかりやすく解説~
こんにちは。
前回は「資産運用のゴール設定」についてお伝えしました。
今回はそのゴールに向けて、特に初心者が実践しやすい代表的な投資商品である「投資信託」について解説していきます。
「名前は聞いたことあるけど、よくわからない」
「NISAを始めようと思ってるけど、どれを選べばいいの?」
そんな声に応えるべく、仕組み・メリット・選び方までを丁寧に説明します。
難しい用語は使わず、「なるほど、これなら自分にもできそう」と思える内容を目指します。
投資信託とは?シンプルに言うとこういうこと
投資信託とは、一言でいうと、「お金をまとめて、プロに運用してもらう仕組み」です。
たとえば、自分ひとりでは100万円も200万円も投資するのは大変ですよね。
でも、たくさんの人が1万円ずつお金を出し合えば、何百万円、何千万円というまとまった資金になります。
この資金を、運用の専門家(ファンドマネージャー)が株や債券などに投資して、出したお金の額に応じて「成果(利益)」を分け合う、というのが投資信託の基本的な仕組みです。
投資に関する専門的な知識がなくても始められるため、初心者の方にとって購入しやすい金融商品といえます。
投資信託の5つの特徴
初心者が投資信託を選ぶ理由は、大きく次の5つです。
- 少額から始められる
→ 100円〜1,000円でもスタートできる。学生でも無理なく始めやすい。 - プロが運用してくれる
→ 経済の知識がなくても、専門家が資産を管理してくれる。 - 分散投資ができる
→ 1つの商品に複数の株や債券が含まれているため、リスクを分散できる。 - 自動積立が可能
→ 月1,000円〜など、自動積立で資産形成が習慣化できる。 - いつでも売却できる
→ 一部を引き出すことも可能で、柔軟な運用ができる。
証券会社によっては、100円から投資信託を購入できます。また、国の財政状況や会社の財務状況などをいちいち調べる必要がありません。「投資=難しい」というイメージを覆す、手軽な資産運用の入り口といえるでしょう。
また、NISAの「つみたて投資枠」を活用すれば、自動で毎週・毎月など決まったペースで投資信託を購入できます。一度設定すればほったらかしで積立投資ができるため、手間もかかりません。
どんな種類があるの?投資信託のざっくり分類
投資信託は、運用の対象によってさまざまな種類があります。代表的な種類は、以下のとおりです。
- 国内株式型:日本企業の株に投資。身近な企業を応援したい人向け。
- 海外株式型:アメリカや世界全体に投資。成長性を重視する人に人気。
- 債券型:国債や社債に投資。安定志向の人向き。
- バランス型:株と債券の両方を組み合わせて運用。バランス重視の人向け。
また、運用の方法には以下の2種類があります。
- インデックス型:市場全体に連動して運用。コストが安く、長期投資向き。
- アクティブ型:プロが積極的に運用し、より高いリターンを狙う。コストは高め。
初心者におすすめなのは、「インデックス型×海外or全世界型」です。理由は、世界中の企業に分散投資できるからです。
投資の世界では、投資先を増やす「分散投資」を行えば、期待リターンを維持しながらリスクを軽減できます。日本だけでなく、海外にも手広く投資をすることで、安定したリターンを期待できます。
また、皆さんは普段日本円を使って生活しており、就職すると円で給料をもらいます。つまり、必然的に円の保有割合が多くなってしまうのです。海外に投資すると間接的に外貨を保有するため、「保有する通貨を分散する」というメリットも得られます。
NISAと投資信託の相性が抜群な理由(深掘り版)
「NISA(ニーサ)」という言葉、聞いたことはあるけれど、「難しそう」と感じる人も多いかもしれません。
ですが、NISAは「これから投資を始める人」を全力で応援する制度なんです。
◆ NISAとは?
NISAとは、投資で得た利益に税金がかからなくなる制度です。
通常、投資で得られた利益には約20%の税金がかかります。しかし、NISAを活用すれば、利益を得た場合でも税金がゼロ。
つまり、増えたお金をそのまま自分のものにできるという大きなメリットがあります。
◆ 制度の概要(学生でも使える!)
| 内容 | 詳細 |
| 利用開始年齢 | 18歳以上(学生OK) |
| 年間の投資上限額 | 360万円 つみたて投資枠は120万円 成長投資枠は240万円 |
| 非課税の期間 | 無期限 |
| 対象となる金融商品 | つみたて投資枠:国が認めた低リスク・長期向けの投資信託など 成長投資枠:株式や投資信託などさまざま |
| 途中での解約や引き出し | いつでもOK。ペナルティなし |
つまり、少額で始めて、長期的に運用していく設計にぴったりなのが「投資信託 × NISA」なのです。
なぜ学生におすすめなの?
学生の方が、早い段階からNISAを活用して投資を始めるとよい理由は、以下のとおりです。
- 収入が少なくても、時間があるから
→ お金が少なくても「複利の力」を使える - 少額から始められる
→ 月1,000円からでもOK。アルバイトの収入で無理なく積み立て可能 - 未来の安心につながる経験値になる
→ 資産運用の感覚を、早いうちから身につけておけるのは大きな強み
以前、複利効果について解説しました。運用期間が長いほど複利効果は大きくなるため、投資は「始める時期が早ければ早いほど有利」です。
社会人になってから慌てて始めるより、大学生のうちに「投資信託+NISA」で習慣を作っておく方が圧倒的にメリットがあります。また、積立投資を継続する習慣を作っておけば、社会人になっても「給与から一定額を投資に回そう」という意識を自然と持てます。
投資信託の選び方5つの視点
投資信託は種類が多いため、次の5つの観点をチェックして選びましょう。
- 投資の目的に合っているか
- 信託報酬(手数料)が安いか(0.3%以下が目安)
- 運用実績が安定しているか(過去3〜5年をチェック)
- リスク分散されているか(全世界や複数資産が◎)
- 自分の性格や生活スタイルに合っているか
投資信託を保有している期間中は、「信託報酬」という手数料がかかります。専門家に運用を頼むため、その手数料と考えてください。
この手数料は、運用成績が良くても悪くても発生します。投資をする人にとって確実に発生するマイナスリターンであるため、できるだけ低コストな投資信託を選ぶのが合理的です。
どんなに優秀な投資信託でも、自分の性格や生活スタイルに合わなければ長続きしません。例えば、値動きが気になって夜も眠れないような人が、ハイリスク・ハイリターンの商品を選ぶと、日々ストレスを感じてしまうでしょう。
投資信託は「一度選んで終わり」ではなく、定期的な見直しが必要です。ライフステージの変化に応じて、これら5つの観点から再評価し、必要に応じて商品の入れ替えを行う必要があります。
よくある質問Q&A
Q. 投資信託って損しませんか?
→ 元本保証はありませんが、分散と長期積立でリスクを抑えることは可能です。
Q. 学生でもNISAを使えますか?
→ はい。18歳以上で証券口座を開設すれば、誰でも利用できます。
Q. 売ったお金は自由に使えますか?
→ いつでも解約でき、使い道に制限はありません。(将来の学費、引っ越し、旅行など自由)
まとめ:投資信託は“最初の一歩”に最適な選択肢
投資信託は、「少額から」「分散でき」「リスクを抑えて」「プロに任せて」資産を増やしていける便利な仕組みです。お金に関する専門的な知識がなくても始められます。
さらに、NISAを活用すれば、税金ゼロ・時間を味方にできる・自動で積み立てが可能です。投資を始めるにあたって、NISAを使わない手はありません。
これから投資を始めたい人は、まずはこの組み合わせからチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
次回予告
次回は、「投資信託とETFの違いと使い分け方」をテーマに、 似ているようで実は性質が異なる“ETF(上場投資信託)”との違いや、賢い組み合わせ方について解説していきます。